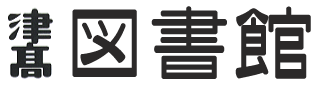車座トーク Vol.40「多様な人が働く時代に~ 共に支え合う社会とは ~」を開催しました
11月12日(水)放課後、車座トークVol.40「多様な人が働く時代に~ 共に支え合う社会とは ~」を開催しました。6人の方にご参加いただきました。話し手は、津地域障がい者就業・生活支援センター「ふらっと」の後藤 勇介さんと川末 依利佳さんです。
まず初めに、医学モデルから社会モデルへ変化した障害者基本法より、「障がい」の捉え方の違いについて教えていただきました。医学モデルにとって「障がい」とは克服すべきものであり、個人の機能障害を治していくことが社会適応の手段となっていましたが、社会モデルでは「障がい」を多様な個性と捉えており、社会側を改善していくことが大切とされていました。
参加した生徒の多くが「障がい」と聞いて、身障者の方を思い浮かべていましたが、「ふらっと」で支援を受けている障がい手帳をお持ちの方のほとんどが精神障害の方なのだと知り、驚きの声があがっていました。インテグレーションとインクルージョンの違いなど、これから社会に出ていく生徒たちにとって、とても重要な知識を学ぶ機会となりました。
講師の後藤さん、川末さん、参加してくれたみなさん、ありがとうございました!
■参加者の感想■
・私は障がいは身体的、知的など見てわかるようなものが障がいと認識していました。けれど、精神的なことで悩んでいる人も障がいを持っているということになると知りました。精神的な障がいは、講師の方がおっしゃっていたように目に見えず、病院での診断や、接し方が難しいところがあるなと感じました。また、障がいについて、中学校の時に国語や道徳の授業で学んだ部分もあり、障がいのある方に問題があるのでなく社会の方に問題があるんだ、という考え方も学びました。また今日のお話からも、発想の転換は大事だなと考えさせられました。
・今まで障害とは漠然と身体につてのものだと思っていたが、そうではなく精神に関するものも含まれるとわかり、自分には固定観念があるのだとわかりました。これからは医学的障害と社会的障害やインクルージョンの考え方を意識して物事を考えていきたいです。まずは学校のエレベーターがないという問題など身近なところから考えていきたいです。
・会話をする場面を用意しながらトークを行ってくださってありがとうございました。自分の障害に対する曖昧な認識を自覚して、周りの環境に障害があるという話にとても納得しました。これからも支援活動を頑張ってください。